この記事では、6月25日に開かれた仮想通貨に関する金融審議会総会の内容についてわかりやすく解説していきます!

注目ポイントは…
「仮想通貨(暗号資産)はお金なのか投資商品なのか」
わかりやすく解説していくよ!
内容を見る前に知っておくこと

なんだかむずかしそうな話になりそうね…

読む前に基本的なことを知っておくと分かりやすいよっ!
「暗号資産」=「仮想通貨」
まず最初に、暗号資産と仮想通貨は基本的に同じ意味です。
2020年に「仮想通貨」から「暗号資産」に呼称が変更されましたが、未だに世間では仮想通貨の方が馴染みがあるためTVやインターネットでは仮想通貨という呼び名が使用されています。
呼び名が変更された理由は、”「通貨」がつくと円やドルなどの通貨だと勘違いされるから”だそうです。
今の仮想通貨の税金事情
2025年6月現在の仮想通貨の所得にかかる税金は総合課税です。
総合課税は仕事の給料や副業収入にかかる税金と同じ扱いなので、仮想通貨の利益はそのまま年収が増えたように扱われます。
例えば、もし年収300万円の人が仮想通貨の取引で年間100万円の利益を上げた場合、年収400万円の人とほぼ同じ分の税金を納めることになります。
その場合、給与から引かれている税金は給与の300万円にかかる分だけなので、仮想通貨の利益にかかる税金を払うために確定申告が必要になります。
| 所得 |
|---|
| 仕事や資産運用などによって得られる利益や収入から、必要経費や控除などを差し引いた「実際のもうけ」のこと。 |
| 総合課税 |
| 給与や年金、不動産収入など複数の所得を合算し、合計額に応じて段階的に税率が高くなる「累進課税」が適用される仕組み。所得が多くなるほど高い税率がかかるのが特徴。 |
今仮想通貨を管理する法律
2025年6月現在、仮想通貨を管理する法律は「資金決済法(資金決済に関する法律)」という法律です。
資金決済法は電子マネーや送金サービスなどを管理する法律なので、仮想通貨は”投資するもの”ではなく”支払いや送金する手段”という扱いになっているということです。
一方で、株や投資信託などは「金融商品取引法」という法律で管理されています。
つまり仮想通貨は、現在の法律上では金融商品ではないということです。
| 資金決済法 |
|---|
| 電子マネーや仮想通貨、前払式支払手段(プリペイドカードなど)のルールを定めた法律。安全に決済サービスを利用できるように事業者の登録や利用者保護を目的としている。 |
| 金融商品取引法 |
| 株式や投資信託などの金融商品の取引ルールを定めた法律。投資家の保護と公正で透明な金融市場を維持することを目的としている。 |
今回注目されていた3つのポイント
今回注目されていたポイントは3つです。
「金融商品取引法」の管轄に変わるのか
1つ目は、仮想通貨を株や投資信託と同じ「金融商品取引法」で管理されるようになるのかということです。
もし仮想通貨が金融商品取引法で管理されると、どのようなことが変わるのでしょうか。
投資家を守るため厳しいルールに
金融商品取引法は投資家を保護することを目的にした法律なので、仮想通貨取引業者には投資家に向けてのリスクの説明や誤解を招くような広告の禁止など、今以上に厳しい制限がかけられるでしょう。
また、仮想通貨に関する不正行為や詐欺、強引な勧誘などは当然今以上に厳しく取り締まられるようになります。
日本で買える仮想通貨の種類が増えるかも
2025年6月現在、世界には約1万7千種類の仮想通貨が存在しています。
そのすべてが誰でも取引できるわけではありませんが、海外の仮想通貨取引所ではそのうちの何百種類かを取引することができます。
しかし、日本の仮想通貨取引所で取引できる仮想通貨は約20~30種類程度です。
日本の仮想通貨取引所で取引できる種類が少ない原因は、日本の今の法律では仮想通貨が投資商品とみなされておらず、取り扱いの基準が明確に定まっていないからです。
もし仮想通貨が金融商品取引法で管理されるようになると金融庁が承認する基準が明確になり、仮想通貨取引所に上場しやすくなる可能性が高いです。
| 仮想通貨取引所(暗号資産取引所) |
|---|
| ユーザーがビットコインなどの暗号資産を売買したり保管できるオンラインのサービス。 |
| 仮想通貨取引業者(暗号資産交換業者) |
| 仮想通貨取引所サービスを提供する会社。日本では金融庁に登録が義務付けられており、利用者の安全を守るための規制が適用されている。 |
| 仮想通貨の上場 |
| 仮想通貨が仮想通貨取引所に承認され、ユーザーが売買できるようになること。 |
「分離課税」が導入されるのか
2つ目は、仮想通貨の税金が見直されて分離課税という制度が導入されるかということです。
もし仮想通貨に分離課税が導入されると、どのようなことが変わるのでしょうか。
税金が一律約20%に
現在、仮想通貨の利益にかかる税金は総合課税で、利益が大きくなるほど税率は高くなります。
例えば、課税所得が1800万円を超えると約50%の税金を支払う必要があります。
最大は課税所得4000万円を超えたときの約55%です。
課税所得には会社の給料も含まれるので、仮想通貨だけではそこまで大きな利益にならなくても会社の給料と合わせるとそれなりに大きな金額になりやすく、税率も高くなりがちです。
もし「分離課税」が導入されると、仮想通貨でどれだけ利益を得ても一律で約20%(所得税15%+住民税5%)の税率になります。
現在の総合課税では所得金額が695万円以上の人は税率が23%なので、それ以上の所得の人にとっては減税ということになります。
反対に、所得が330万円以下の人は税率が10%なので、それ以下の所得の人にとっては増税になってしまいます。
| 分離課税 |
|---|
| 株式の譲渡益や不動産の売却益などの所得と他の所得を分けて独自の税率で課税する方式。税額を支払時に源泉徴収する「源泉分離課税」と、確定申告で税額を計算する「申告分離課税」がある。 |
確定申告が不要に
現在、サラリーマンの人でも会社の給料以外で年間20万円を超える利益が出ると確定申告が必要になります。
当然、仮想通貨の利益も当てはまるので、これが仮想通貨に手を出しにくい理由の一つになっています。
一方で、分離課税の株や投資信託には、証券会社が税金を源泉徴収して収めてくれるくれる仕組み(=源泉分離課税)があります。
もし仮想通貨が株などと同じく分離課税になると、確定申告がいらなくなる制度がつくられる可能性があります。
そうなれば、原則として確定申告をする必要がなくなり仮想通貨のハードルがやや低くなると言えるでしょう。
| 確定申告 |
|---|
| 1月1日~12月31日の所得をもとに税金を計算して自分で税務署に申告・納付する手続き。自営業者や副業収入がある人が対象。 |
| 源泉徴収 |
| 会社や取引業者があらかじめ税金を給料や利益から差し引いて、本人に代わって税務署に納める仕組み。 |
「仮想通貨現物ETF」が日本国内でも買えるようになるのか
3つ目は、仮想通貨の現物ETFが日本国内でも買えるようになるのかということです。
もし日本で仮想通貨の現物ETFが買えるようになるとされると、どのようなことが変わるのでしょうか。
簡単に仮想通貨に投資できる
仮想通貨現物ETF(暗号資産現物ETF)とは、仮想通貨の代表的な存在である「ビットコイン」など仮想通貨の実際の価格に連動して動く投資信託のことです。
仮想通貨現物ETFをわかりやすく言いかえると、仮想通貨を直接買わず、仮想通貨に投資するプロ集団に間接的に投資できる仕組みだと考えてください。
これにより、仮想通貨を直接買わなくても仮想通貨市場に参入することができるようになります。
アメリカでは2024年にすでに仮想通貨現物ETFが承認されており、これまでに投資された金額は合計で数十~数百億ドルにもなっています。
ただし、アメリカで承認されている仮想通貨現物ETFを日本国内から買うことは今のところできません。
| ETF(上場投資信託) |
|---|
| 証券取引所で個別株のように取引できる投資信託。通常の投資信託より信託報酬が低いメリットがある一方で、需要と供給に応じて価格が変動しやすいというリスクもある。 |
今回話し合われた内容をわかりやすく解説
ではここまでを踏まえて、今回の審議会の資料「暗号資産を巡る制度のあり方に関する検討について」の内容を確認していきましょう。
日本でも暗号資産を持つ人が急増中
国内では、暗号資産交換業者における口座開設数が延べ1,200万口座超、利用者預託金残高は5兆円以上に達し、投資経験者の暗号資産保有者割合は約7.3%で、FX取引や社債等よりも保有率が高くなっている。
日本ではすでに仮想通貨の口座が1200万以上も作られていて、預けられているお金は5兆円以上にもなっているようです。
投資をしない国民性と言われる日本人ですが、ここ数年で仮想通貨がかなり浸透してきているようです。
すでにFXよりも仮想通貨を持っている人の方が多いというデータが紹介されています。
仮想通貨のトラブルも増加中
金融庁の「金融サービス利用者相談室」には、詐欺的な暗号資産投資の勧誘に係る相談等が継続的に
寄せられている状況(足下、暗号資産等に関する相談等は月平均300件以上)。
出典:金融庁「暗号資産を巡る制度のあり方に関する検討について」
金融庁の「金融サービス利用者相談室」に寄せられる相談の約1割が仮想通貨に関するものだそうです。
- SNSで知り合った人やグループから「儲かる」と勧められて仮想通貨に投資したがその後出金できない
- 「必ず値上がりする」「高配当が得られる」と言われ無名の仮想通貨を購入したが実際は取引ができるものではなかったため売ることができない
という実例が資料の中で紹介されています。
何事も人気が出てくると必ずそれを悪用する人が出てくるものです。
金融商品取引法の管轄を検討
暗号資産投資を巡る喫緊の課題
- 情報開示・提供の充実
- 利用者保護・無登録業者への対応
- 投資運用等に係る不適切行為への対応
- 価格形成・取引の公正性の確保
は、伝統的に金商法が対処してきた問題と親和性があり、金商法の仕組みやエンフォースメントを活用することも選択肢の一つ。
現在の日本における仮想通貨は、トラブルに繋がりやすい課題をいくつも抱えています。
資料に書かれているものをわかりやすく言いかえると、
- 大事な情報がすべて購入前に明かされない
- 金融庁が認めていない業者が無登録で商売している
- 小規模な仮想通貨が一部の組織によって不正に価格操作される
- 一部の投資家に対して不公平な取引がある
といった具合です。
実はこれと同じ問題は、株式や投資信託の歴史上でも過去に起きていました。
そして、それらに対応するため世界中で金融商品に関する法律が整備されてきました。
日本では金融商品取引法がそれに当たります。
つまり、仮想通貨が抱える課題を解決するためには金融商品取引法で管理した方が良いという見解が示されています。
しかし、すべての仮想通貨をすべて一括りに金融商品取引法で管理するのではなく、投資に適したものとそうでないものを分けて考えるべきだという意見も紹介されています。
分離課税の導入を検討
諸外国の動向も踏まえつつ、暗号資産を国民の資産形成に資する金融商品として業法において位置付けるとともに、投資家保護のための制度を整備する法案の早期国会提出を図りつつ、税務当局への報告義務の整備などを行った上で、分離課税の導入を含めた税制面の見直しの検討も併せて行う。
金融庁としては正式に分離課税を検討すべきであると明記されており、かなり前向きにとらえていることがわかります。
もし導入されると高額な投資を行う機関投資家などにとっては嬉しいニュースです。
しかし、実は金融庁は今年2月に、仮想通貨の分離課税導入に向けて検討を開始するとすでに発表しているのです。
そのため今回の審議会では導入時期など具体的な内容が発表されるかが期待されていました。
そういう意味では、“検討”のまま状況は変わらずだったとも言えます。
アメリカの仮想通貨現物ETF承認を評価
暗号資産(仮想通貨)ビットコインを組み入れた米上場投資信託(ETF)を保有する機関投資家の裾野が広
がっている。日本経済新聞の調べでは、3月末比で2割増え、1200社を超えた。公的年金など長期保有を前提
にする投資家が金(ゴールド)と同様にインフレ耐性の資産として投資する動きが増えている。
アメリカが2024年に仮想通貨の現物ETFを承認したことを高く評価していることがわかります。
仮想通貨は、金と同じようなインフレ耐性資産(インフレで価値が上がる資産)としての評価され始めているようです。
特に、代表的な仮想通貨「ビットコイン」はすでに金と比べられることが多いです。
しかし、日本が仮想通貨の原物ETFを認める方向かどうかという肝心なところは何も触れられていませんでした。
注目されていたポイントはどうなる?

資料の内容から、
- 「金融商品取引法」
- 「分離課税」
- 「仮想通貨現物ETF」
この3つか今後どうなるかを予想してみたよっ!
金融商品取引法の管轄は早くて2027年と予想
今回の内容では、仮想通貨が抱えている問題の解決には金融商品取引法で管理する必要があるという見解が随所に見られます。
仮想通貨が金融商品取引法で管理されるようになる可能性はかなり高いと言えます。
ただし、このまま話がスムーズに進んだとしても、今年2025年12月の税制改正大綱に載り、来年2026年中に国会で審議され可決、早くても2027年から開始になると予想できます。
分離課税は金融商品取引法の管轄と同じタイミングと予想
金融庁は今年2月からすでに仮想通貨の分離課税導入に向けて検討していることからも、分離課税の導入は十分現実的であると予想できます。
今回具体的な時期などはありませんでしたが、それは法律を変えるため国会で審議をする必要があるので、まだ金融庁が時期を示すことが難しい段階だからでしょう。
タイミングはおそらく金融商品取引法との管轄になるのとほぼ同時で、早くて2027年の以降になると予想できます。
仮想通貨現物ETFは最短で今年中に国内解禁?
さて、今回の内容で一番触れられていなかった仮想通貨現物ETFですが、これは2026年、早ければ今年2025年中にも解禁される可能性があると思います。
その理由は、金融商品取引法の管轄や分離課税と違って法律を変えなくても実現できるためハードルが低いからです。
金融庁が認めれば、必用なのは証券取引所と証券取引等監視委員会の審査を通過することだけです。
金融庁がもう仮想通貨を資産として扱っていく方向なのは間違いないので、アメリカで実績があって法改正がいらないETFの承認から着手していく可能性は十分考えられます。
まとめ
- 仮想通貨が金融商品取引法で管理される可能性は非常に高く、早ければ2027年中と予想。
- 分離課税の導入も高い可能性があり、金融商品取引法の改正と同時期で早くて2027年中と予想。
- 仮想通貨現物ETFの承認は法改正がなくても可能なため、2025年内から2026年に実現する可能性が高い。
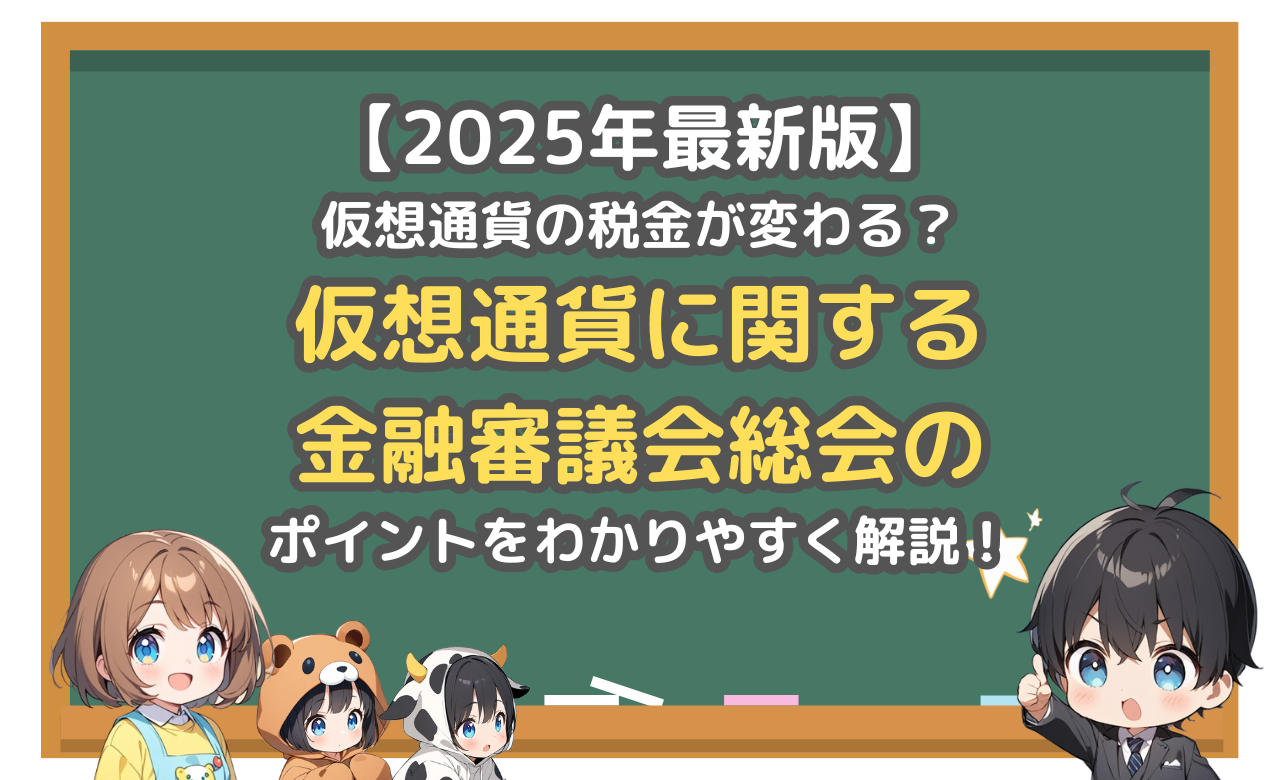
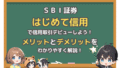
コメント